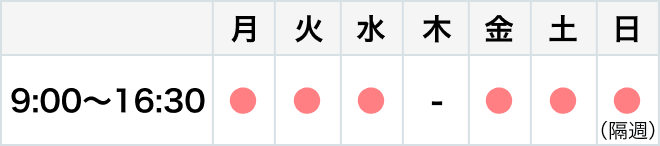フロイトの“死の本能”
前回は生の本能についてお話ししました。今回は、対になった概念であり、1920年に提出された“死の本能”(『快感原則の彼岸』)について。彼は「本能とは生命ある有機体に内在する衝迫であって、以前のある状態を回復しようとするものであろう」と、死んで無機物に還るという仮定により、あまねく生命の目標は死なのだ、と述べたのです。「まぁ細胞もアポトーシスするしなぁ…」と納得しかかってしまいそうですね…。
この死の本能はあまりにも思弁的であり(フロイト本人も「思弁である」と但し書きをしています)、後の精神分析家の間でも賛否両論。“賛”の方でもフロイトオリジナルの死の本能を薄めて(?)、生来性の破壊衝動を単に指していることが多いように思います。それが外に向かうと敵意や攻撃性になりますし、自分に向かうと自殺や自己否定などになります。ちなみに、木村敏先生は、Freudの言う死の本能の“死”とは、大文字の〈生〉―私たち小文字の生を生たらしめる、決して死なない生命それ自身―を指していると述べています。“決して死なない生命それ自身”は、個体化した“私”から見たら生というよりも死である、つまり生=死、なのですね。この大文字の〈生〉(=死)を“ゾーエー”、小文字の生を“ビオス”と呼びます。エヴァンゲリオンで例えるならば、ゾーエーはL.C.L.であり、ATフィールドを纏った個体がビオスとなる、と考えてもいいのではないでしょうか。また、ゾーエーは西田幾多郎(にしだきたろう)の“絶対無”でしょうし、メルロ・ポンティなら“肉”、スピノザなら“神”がそれに近いと私は考えています。