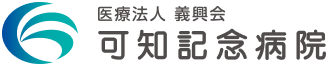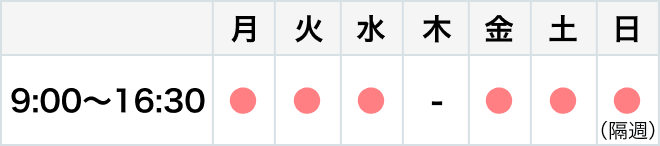今回のブログは医局が担当します。
啓蟄(けいちつ)
寒かった今年の冬もようやく終わりが見え、日中は日差しの暖かさも感じられるようになりました。
二十四節気という日本の24の暦があります。
このうちよく耳にするのが、春分・秋分、夏至・冬至など。
これらは一年を24等分した分割点を含む「日」に、季節を表す名前をつけたものだそうです。
立春、小暑・大暑、小寒・大寒などは、その季節の気候や風景も浮かんできそうです。
二十四節気の中に、啓蟄(けいちつ)というものがあります。
立春→雨水→啓蟄→春分と順に続く並びの中にあって、だいたい3月4日〜6日頃にあたります。
子どもの頃、どこかで(図鑑か、小説か、もう記憶も朧ですが)目にしたこの2文字の言葉。
難しい漢字に興味を持っていた当時、不思議と惹きつけられ記憶に刻まれています。
「啓」は「ひらく」、「蟄」はつくりに虫が入っているように「虫が土中にこもる」の意味。
「啓蟄」で「冬籠りの虫が這い出す」すなわち春の訪れの走りの時季を表すと知りました。
電波時計が身近になり、事象を何でもデジタルで表せる時代ですが、二十四節気のようなざっくりとした季節の迎え方も、味わいがあって良いと思いました。