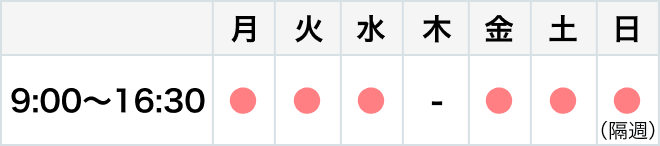精神分析における関係性
関係性理論
前回お話ししたようなコフートの論をきっかけに、1980年代から精神分析の“関係性理論”が花開いていきました。客観主義は構成主義へと変化し、患者さんと治療者のこころはお互いに影響し変化し続けるものであり、その過程をそのまま把握するようになっていったのです。私は先に精神分析の発達理論を述べましたが、そこでは精神病理が重ければ重いほど早期の発達に問題があるというのが前提でした。しかし、現代の精神分析、特に関係性理論においては、患者さんに見られている病理は今の治療者との患者さんとの関係で共につくられたものであって、発達上の問題が必ずしも反映されているわけではないと考えます。「そりゃそうだよなぁ(当たり前だよなぁ)」と思いますが、精神分析ではずっと「今の問題は過去の反復だ! 無意識の中を探って、発達の中に見られる問題点を解釈によって伝えて洞察を促していくことが大事だ!」という教えだったのです。患者さんは人生の台本に忠実に沿っている、というアタマがあったのですね。現代はそうでなく、台本があるにはあるけれども結構スカスカで明確なプロットも実はないし、即興も多くて、そこに治療者も参加してわいわいやっていけちゃうよ、という感じになりつつある、と言えるでしょうか。
間主観性
現代の精神分析は“間主観性 intersubjectivity”に向かっています。間主観性と言っても2種類に大別されるようで、ひとつの流れはストロロウやアトウッドやオレンジによるもの、もうひとつはベンジャミンやミッチェルによるもの。前者は、二人の主観的世界は常にお互いの主観的世界に影響を受け、変化を止めない流転のものである、という考えに基づいています。後者はそれよりも二人の独立性を強調していて、正しい唯一の答えはなく、文脈において両者の相違点と共通点を見つけその意味を見出していく、という過程を描きます。いずれにしても、唯一の正解が患者さんの奥底に眠っており精神分析によって洞察が得られる、という古典的な考え方からは離れます。それは、とても不確実でしょう。お互いの影響を考える、文脈で考える、というのは、足元がふわふわとしています。どこか心許なく、つい何かに、大きな既存の理論(権威)に頼ってしまいたくもなるでしょう。そこを何とか堪えながら、患者さんとのあいだでの出来事を考えていかねばなりません。精神分析も大変な時代に入ってきたのだな…と他人事ながら思っています。