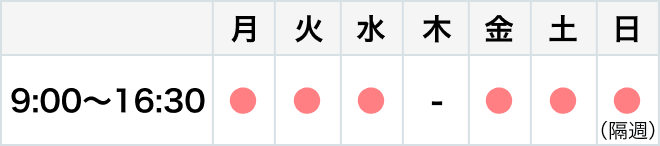精神分析(フロイトからコフートへ)
フロイトの精神分析
精神分析はフロイトから始まり、カーンバーグ、クライン、ビオン、ウィニコットなどが発展させてきました。それによって、精神分析は対象を神経症からパーソナリティ障害、うつ病、そして統合失調症まで射程範囲を広げたことになります。以前にフォナギーとベントマンによるメンタライゼーションを紹介しましたが、ここで強調したかったのは、患者さんは過去の反復を生きているのではなく、必ず今の治療者とのあいだが関わっているのだということ。精神分析は、より人と人との関係性に舵を切っていると言えるでしょう。今回と次回は現代の精神分析がどうなっているのかを眺めておきたいと思います。
コフートの精神分析
ここで登場いただくのが、コフートです。彼は伝統的な精神分析家だったのですが、1960年代中盤からの仕事はアメリカ精神分析のパラダイムシフトを起こしたとも言われます。伝統的な精神分析では、治療者は客観的な科学者であり、分析理論という真理に則り患者さんの内的世界を外から観察していくという手段でした。アメリカではこのようなフロイト直系の自我心理学が盛んだったのですが、コフートは“共感”によって患者さんの中に入り込んでいくという手法をとったのです。そこでは、治療者もまた観察対象の一部であり、自分が見ている患者さんの病理は常に相対的なものである、という強調がなされました。フロイトから続く客観主義に対して精神分析の内部から異を唱え続けたというのが驚くべき出来事だったのです。
初期のコフートは、精神分析とは何かを論じている中で、「共感とは相手のデータを収集するための道具であり、それは相手の主観性を知るために用いている能力なのだと」いう旨を述べています(『コフート入門』)。そして、そのデータというものは、治療者の主観を通してのみ得られる患者さんの主観的な世界であるとも強調しています。ここがとても大事で、上述のようにこれまでの精神分析とはまったく異なることを言っています。私たちが“客観”と呼んでいる現象は、結局は主観の集合なのかもしれませんね。そして、受け取ったデータが適切なのかどうかは、本人と話し合ってみなければわからないものであり、話し合ってみてもわからない場合があります。そのため、そのデータについて二人できちんと探っていく必要があるよ、ということを彼は付言しています。指導医から「いいかぁ、共感が大事だぞ」と言われても、わかったようなわからないような印象が拭えないのですが、コフートのように“データ収集の道具”と言ってくれるとそのファンタジー的な感じがなくなりますね。ただ、治療者の主観を通して行なわれるという部分を決して忘れてはならないのです。
後期に入り、コフートは共感を“人どうしの心の反響”や“人どうしの強い情緒的結びつき”と定義し、他者との関係性をより強調しました。また、“自己”や“自己対象”という用語にもそれが表れています。彼の言う“自己 self”とは、「空間的に凝集し時間的に連続する一つの単位であり、それは自主性の中心であり、印象の受け手である」というものです(『自己の修復』)。なんとも曖昧ですが、実際に存在する“私自身”ではなく、体験的なものと理解されてます。では、“自己対象 selfobject”とは何か。これも実在の人ではなく、主観的な体験を指しています。ストロロウらの定義がよりスッキリしていて、彼らは“自己”を「主観的自己体験」とし、“自己対象”を「対象体験の一側面であり、主観的に体験された対象であり、自己体験の保持、修復、変容に関わる一群の心理的機能」としています(『間主観的アプローチ』)。このように、体験という面を強調していることから、主観性と主観性とが関係するその文脈こそが重要なのだ、と言えるでしょう。