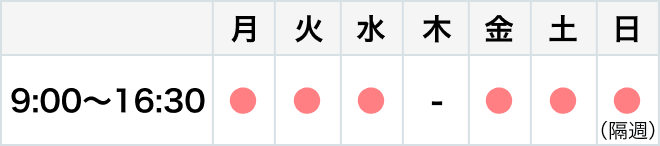今回のブログは医局が担当します。
了解を活かせるか
了解可能か了解不能か、それはとても難しいこと。かつ、この“了解不能”、特に統合失調症の了解不能は、患者さんへの接近の諦めとも受け取られてしまいがちです。「語り得ぬものについては沈黙しなければならない」と言わんばかりに。それじゃいけませんよ、ということで、クレッチマーは多元的な理解を促し、他にも哲学を応用した学者が複数誕生したのは以前に述べたとおりです。“語り得ぬものを語ろうとする努力”とも言えるでしょうか(いや、そもそも語り得ぬものなのかどうか)。これは学問への態度の違いとも表現できます。ヤスパースは、精神病理学はあくまでも学であるべきだというスタンスを保っていました。『精神病理学原論』でも、このような記述を見ることができます。
精神病理学者にとっては学問それ自体が目的である。精神病理学者はもっぱら、知ること、認識すること、特徴づけること、分析することだけを目指しているが、その対象は一人一人の人間ではなく、一般的なもの、普遍的なものなのである。
いっぽうで、「精神科医にとって学問はただの補助手段に過ぎない」という記述もあり、彼は実地の精神科臨床と精神病理学とを明確にわけていました。ヤスパースにとって、“了解”は学におけるひとつの手段であり、道具であったと言えます。「患者さんへの理解を深め、共感しましょう」というサイコセラピー的な態度として了解を用いたわけでは決してありません(特に初版はその傾向が強いですね)。その後、ヤスパースは哲学者となりましたが、『精神病理学総論』の改訂を続け、実質的な最終版である第4版では“人間存在の全体”という哲学的な項目をつくりました。これにはシュナイダーはじめハイデルベルク学派の皆さんはガッカリしたそうですが、精神病理学から少し外れた部分を加えたところに、彼の精神科臨床への憧憬が見え隠れするような、そんな印象を私は持っています。Psychopathologyは“-logy”であり“logos”があるのですが、Psychiatryの文字にはその文字がなく、“logos”からの解放を示しているかのようです(そもそもlogosになれていないという意見も?)。精神病理学は人間のいくつかの側面を把握できるだけであり、その存在全体を把握はできない、ということを哲学者となったヤスパースは述べています。
では、現代の精神科臨床において“了解”はどう扱われるべきでしょう? 私としては、多くの場合は診断というよりもサイコセラピー的な側面として採用すべき、と考えています(ヤスパースとは異なりますが)。仮に“神経症”であっても、一人の人間のこころの動きをすべて了解できることはなく、必ず了解可能な部分と了解不能な部分が、程度の差こそあれ混在しているでしょう。それをきちんとわけていこうとする態度は、必然的にサイコセラピーになるのです。患者さんをわかろうとすること、わからないところをわかるところまで辿っていくこと、残った“わからないところ”は大事なものとして取っておくこと。このために“了解”は使用されるべきではないでしょうか。