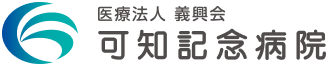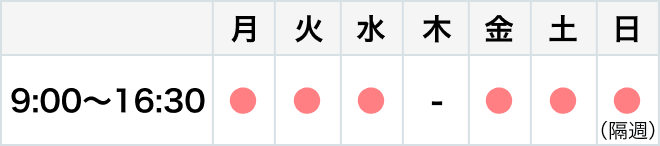豊橋市の精神科の可知記念病院です。
今回のブログは検査課が担当します。
採血スピッツの違いについて
皆さんは採血をする際、採血管に注目したことはありますか?
「今日は何本も取られるなぁ」と思ったことがある方もいるかもしれません。
採血管にはいくつかの種類があり、それぞれ用途が異なります。
複数の種類の採血管で採血しなくてはならないのは、そのためです。
今回のブログでは、そんな採血管の種類と用途についてお話しようと思います。
主要な採血管は以下の通りになります。
用途 抗凝固剤
〇凝固系検査 クエン酸ナトリウム
〇生化学検査 血清分離剤入り
〇血算 EDTA
〇血糖 解糖阻害剤入り
〇その他 ヘパリン
抗凝固剤とは、その名の通り、血液が固まらないようにする薬剤です。
検査の中には、
血液が固まってしまうと測定不能になってしまう項目も存在します。
そのため、検査項目に適した抗凝固剤を用いて、
採血した血液を固まらないようにします。
抗凝固剤によって様々な特徴がある為、適した検査項目が異なり、
その結果、検査項目に合わせて複数種類の採血管での採血が必要となります。
採血後、看護師や検査技師が採血管を振っている様子を見たことがあるでしょうか?
あの行動は、採血管の中に入った抗凝固剤や血清分離剤などの薬剤と、
血液を混ぜるために行っている大切な行為です。
今回のブログはここまでとさせていただきます。
ありがとうございました。