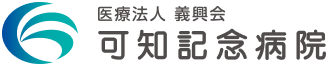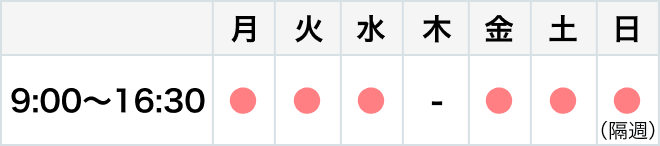豊橋市の精神科の可知記念病院です。
今回は医療相談室が担当します。
精神疾患・精神保健福祉の歴史(日本編①)
以前のブログで古代~中世編として精神疾患および精神保健福祉の歴史を紹介しましたが今回からは日本の歴史について紹介します。
日本では、精神障害のことを病気とする考え方がかなり古くからあったようです。
759年、桓武天皇の時代に編纂された、日本最古の医学書とされる「藥經大素(やくきょうたそ)」には、漢方薬の薬効のひとつとして、精神症状に関する記載があるといわれています。
700年代のころにはすでに、“精神の異常は薬物による治療の対象である”という考え方が中国から伝わっていたということになります。
中世以降になると、民間療法も行われるようになります。
“治療”として寺院に収容されることが多かったようですが、
すでに精神疾患をもつ患者を収容していた寺院から、次第に精神疾患の治療に賛同する寺院が増えていきます。
寺院での治療に際して、まず患者は、家族や関係者に引率され寺院を訪れ、治療に関して相談をしていきます。治療は寺院側が強制するのではなく、祈祷か、灸法か…など、どのような治療が良いのか、患者側の希望を聞きとりながら決められていたようです。
炊事や裁縫など、今でいう作業療法に近い治療をする寺院もあったといわれています。
その中でも多かった治療法は水治療といわれるもので、滝打ちや河川での沐浴、井戸水を浴びせる…など、冷水浴をさせることが多かったといわれています。
続きは次回、医療相談室ブログで紹介します。