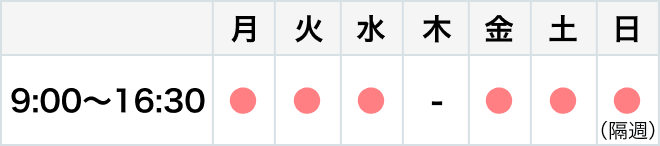今回のブログは医局が担当します。
自閉スペクトラム症における感覚の問題
自閉スペクトラム症を有する患者さんの多くは、感覚の問題を持っています。
DSM-IV-TRまでは診断基準に入らなかったのですが、ついにDSM-5でB項目に取り上げられました。
そして、患者さん1人1人で何に対して鈍麻/過敏なのかは全く異なります。
鈍麻/過敏と述べましたが、患者さんには感覚鈍麻と感覚過敏という、相反するような症状が認められます。
実に様々ですが、特に感覚過敏は身体症状症と診断されることがあります。
感覚鈍麻と感覚過敏は混在もしますが、自らが「感覚過敏で困る」と認識できる(してしまう)ようになるのは成長してからが主のようです(10歳前後から徐々にという印象)。
自閉スペクトラム症はシナプスの過剰が示唆されているように、情報で神経回路が渋滞してしまっているのが基盤にあると思ってみましょう。
目の前の光景がすべてになってしまい、それによる主客未分が様々な症状につながります。
感覚鈍麻は、感覚とも未分になっている、感覚と合一の状態になっていると言い換えられます。
そのため、主客未分を引きずる自閉スペクトラム症では、初期に感覚鈍麻が目立つのだと思われます。
感覚過敏が初期にあったとしても、それを感覚過敏とは自覚されないことが多いのかもしれません。
周囲にとってその現象を感覚過敏だとはなかなか理解できない時、周囲がそれを照らし返せません。
その現象はまだ彼らにとって“何か”であり、“感覚過敏である”と分節化されないのです。
“何か”は“何か”のままであり、名付けられていないのです。
よって、症状とならないのでしょう。少し細かく説明をしてみます。
人が“何か”を“分かる”というのは、“何か”という現象から常に一歩遅れて立ち現われます。
“何か”が生じると、周囲(主に母親)が「お腹空いた?」「痛いですねー」などと言葉を与えます。
それが繰り返されることで、“何か”に“名前”が付与されていきます。
「そうか、この“何か”は、お腹が空いているというのか」「痛いってこういうことなのか」と、モヤモヤした何かに言葉が意味をもたらすのです。
このように、感覚を感覚だと分かることは、感覚と同時に起こるものではなく、常に遅れます。
感覚過敏については、主客未分がベースにあり感覚との距離が形成されにくい自閉スペクトラム症の特徴に加えて、周囲からも言葉によって意味が与えられないため、患者さんが「感覚過敏だ」と理解する(症状化する)には時間がかかってしまうのです。
感覚が感覚だと分かるには、それが言葉によって切り取られねばなりません。すなわち、主客の存在を知らねばならない(自閉スペクトラム症にとってそれは何となくの主客を学び獲得することにはなりますが)のです。度重なる苦闘の果てに得た主客の知識は、今度は感覚の存在に目覚めさせます。神経回路にひしめいていた過剰な“何か”が感覚なのだと分かると“感覚過敏”になる、そう考えられます。幸か不幸か気づいてしまったがために、感覚鈍麻から感覚過敏へとシフトするのかもしれません。